「スリヴァー(Slivers!!)」デッキ解説⑤
2018年9月17日解説も第5回と長くなりましたが、今回はサイドボードについて書いていきます。
なお、当初は解説のみで終わらせる予定でしたが、せっかくなので第6回までとして、いくつかのマッチアップの in&out とゲーム進行の方針まで書こうと思います(時間はかかるかもしれませんが…笑)。
さて、スリヴァー・デッキのサイドボードはおおまかに二つの流れがあり、一つ目はスリヴァーを中心とする構成、二つ目はスリヴァーをある程度の枚数に絞って、シナジーはないけれど有効な対策カードを採用する構成に大別されます。
それぞれに一長一短があり、前者は他のスリヴァーとのシナジーを維持しているためクロックが落ちにくいものの、サイドボードの効果としては限定的、後者は効果が強力な反面、シナジーに乏しく(スリヴァーが複数体並ぶことを前提とした構築では)クロックが細くなりがち、という特徴があります。
私は後者の構成をとっており、サイドボードの機能としては、(プレイのしやすさなどは前提としつつも)刺されば1枚でも勝てる尖ったものを優先すべきだと考えています。ただ同時に、サイドボードを作る際にはそうした1枚で勝てるカードを中心としつつも、他のデッキへ転用できるカードも採用して補助する形としています。
こうした考えは、サイドボードの枚数に対してアーキタイプの数が多いモダン特有の条件下で、非常に重用だと感じています。なお、モダンのデッキが全体的に高速化する傾向もこのあたりに原因があります(=速度で上回れば〈採用枚数が限られた〉数枚の妨害はさほど問題にならない)。
効果的なサイドボードを作るには、まずは環境を渉猟してもっとも効果的と考えられるカードを探し出すことが必要ですし、このデッキにはこれ、あのデッキにはこれ…と考えるのではなく、ある程度環境のデッキを類型化し、このタイプのデッキにはこれ、といった考え方が必要になってきます。
その他、モダンは主要なアーキタイプ以外のデッキも多いため、状況にあわせて柔軟に考えられる構成や訓練も必要ですね(それでも、サイドが30枚くらい欲しくなる時がありますが…笑)。
それでは具体的に第1回の画像にあげたサイドボードを機能毎に解説していきます。
ただし、前述のようにモダンのサイドボードは15枚ではとても足らず、絶えず細部が変わっています。現段階(2018年9月)では、ブリッジヴァイン・青白コントロール・5C人間などの支配率が高いため、それぞれ、虚空の力戦の増量、思考囲いの数の調整や使用可能な専用サイドの選定(沸騰、ガドック・ティーグ、情け知らずのガラクなど…)、倦怠の宝珠の採用などの変更をおこなっています。また、M19の加入に際して、タイタンシフトに対して効果の薄かった大爆発の魔導士を高山の月に差し替えるなどの変更もおこないました。そのため必ずしも第1回の画像の通りとはならないことをご了承ください。
(1)墓地対策
虚空の力線 2(〜3)
大祖始の遺産 1
墓地対策は3~4枚をメタゲームを見て調整しています。虚空の力線の採用・枚数については疑問に思われることもあるでしょう。
まず力線を優先している理由は、単純に他の墓地対策では間に合わないケースが増えてしまったことがあげられます。
例えばグリクシスシャドウの先手・思考掃きからの2ターン目タシグルや、ドレッジの1ターン目傲慢な新生児からの発掘、ホロウワンの1ターン目虚ろな者からの炎跡のフェニックス&恐血鬼、ブリッジヴァインの1ターン目復讐蔦…など枚挙にいとまがありません。同時に青赤ストームやグリセルシュート、マルドゥパイロマンサーなどへもある程度対策になるのも大きいです。
次に枚数ですが、これは完全にサイドボードの枚数との関係です。もちろん初手にないことも往々としてありますが、それでも力線は出れば大きく有利にゲームを進められ、他の墓地対策に比べてリターンが大きいため優先して採用しています。というかそもそも、現在のモダンでは初手にない墓地対策はそれほど強くない…と割りきって使っています。ここの枚数は上記のデッキがどれくらいいるかの予想によって変動することになります。
一方、大祖始の遺産は虚空の力線とは若干用途が異なり、ジャンド(タルモゴイフ・漁る軟泥・渋面の溶岩使いなど)や青系コントロール(瞬唱の魔道士・アズカンタの探索など)対策として使うことも想定して、散らせて採用しています。対ジャンドや青系コントロールでは力線がハンドアドバンテージを失いやすくそもそもサイドインできないのに対して、遺産はドローにも変えることができて無駄牌になりにくいのが利点です。
なお、墓地対策のパターンは環境にともなって変化しており、少し前は以下の形で使い分けをしていました。
大祖始の遺産 1
虚無の呪文爆弾 1
外科的摘出 1
遺産は前述のように無駄牌になりにくい墓地対策として。他方、遺産は墓地に特化したデッキ相手だと後手で間に合わないこともあったので、呪文爆弾を(1ドローを放棄すれば)後手でも間に合う墓地対策として採用していました。また外科的摘出はグリセルシュートやアイアンワークスなど特定1種のカードを取り除くと動きが遅くなるデッキや、瞬唱を使う青系コントロール用としての役割でした。効果は限定的ですが対ドレッジ戦などでも最初の発掘カードや燃焼を追放するためにサイドインしていましたね。
(2)土地系コンボ対策
大爆発の魔道士 2(or 1枚を高山の月に差し替え)
減衰球 1
この枠は主にトロン系(緑単・青)やアミュレットタイタンなどへの対策用です。大爆発の魔道士は対コントロール、減衰球は青赤ストームやアイアンワークスへの対策としても転用できます。
ただ、以前のコントロール型のスケープシフトに対しては大爆発2枚でも対抗できましたが、タイタンシフトの登場以降、適切かつ有効なサイドを確定できていません。
大爆発1枚を血染めの太陽に差し替えたこともありましたが、トロンへの対策が薄くなることがネックで結局不採用となりました。現在はトロン・タイタンシフト双方に干渉することのできる高山の月の採用を試行中です(置物のため直接破壊するより信頼度は下がりますが…)。
(3)アーティファクト・エンチャント対策
調和スリヴァー 2
戦争の報い、禍汰奇 1
調和スリヴァーは、すべてのスリヴァーに「戦場に出たとき、アーティファクト1つかエンチャント1つを対象とし、それを破壊する」能力を共有します。
スリヴァー・デッキにとっては最上とも言えるサイドカードで、このカードのおかけで、親和(鱗親和含む)・呪禁オーラ・テゼレットコントロールなどに対して優位にゲームを進められます。
特に対親和は、サイドプランのギラプールの霊気格子にも対応でき、さらにスリヴァーの巣があれば無色のスリヴァー・トークンに能力を共有して、刻まれた勇者といったプロテクション持ちも破壊できるようになります。
その他、対トロン(忘却石など)・対青系コントロール(アズカンタの探索・拘留の宝球など)などのマッチアップでもサイドインすることができます。
ただし、この能力は再利用の賢者などと違って強制のため、場合によっては自分のものを破壊する可能性もあることに注意しましょう。また、相手の場にダークスティールの城塞などがある場合は、それを対象にとることで前述の事態を回避することができます。
一方、禍汰奇は完全に親和専用のサイドボードになります。前述の調和が3マナのため、後手で遅れないように1枚を補助用に採用しています。1度でも誘発させることができれば盤面・テンポともに大きなリターンを得られますが、相手の感電波を意識する必要やマナベースの問題もあるなど、リスクがないわけではありません。最近は鱗親和の増加など親和のバリエーションも増えつつあるので、採用する優先度は相対的に低くなっています。
(4)コントロール対策
思考囲い 2
魔術遠眼鏡 1
ウルザの後継、カーン 1(or 情け知らずのガラク 1)
思考囲いは対コントロールだけではく、対コンボや対トロン、霊気の薬瓶をサイドアウトする対ミッドレンジでのマッチアップ(ジャンド・アブザン・マルパイ…)など広範囲にサイドインできます。ただし、土地からのダメージと合わせるとダメージレース的に厳しい場合があるので、マッチアップによっては先手のみでサイドインする場合もあります。
魔術遠眼鏡は元々真髄の針だった枠で、対PWが主な役割です。以前にトリコナヒリが流行した時の名残ですが、現在も神ジェイスやテフェリー、ウギンなど対処できない=負けのPWが存在することから、枠を継続しています。
その他、献身のドルイドや渋面の溶岩使い、電結の荒廃者、鋼の監視者などのシステムクリーチャー、また仕組まれた爆薬、忘却石、ミシュラランドといったカードにも広く干渉できるため、専用サイド+αの形でサイドインが可能です。
真髄の針との優劣については、針が後手の時にも対トロンの探検の地図に干渉できたり、コストによるテンポ面で優れている面もありますが、指定を外してしまった場合のリスクを加味すると、ゲームプランを立てやすい眼鏡の方が優れている、という結論になりました。
その他、この枠としてはファイレクシアの破棄者も候補にあがります。こちらはクリーチャーのため信頼度は下がりますが、針・眼鏡と違って(土地は指定できないけれど)マナ能力も封じることができたり、薬瓶や集合した中隊との相性も良好です。とくにマナ能力も封じれる点は、クラーク族の鉄工所やカウンターカンパニーのマナクリーチャーなどへも干渉でき、サイドボードの幅が広がると思われます。
ウルザの後継、カーンは、サイド後にコントロール側がカウンターを減らす or 払拭に差し替える、あるいは全体除去を増やすことを見越して採用しています。
マナベースの関係上、スリヴァー・デッキではダブルシンボル以上のPWの採用は難しかったのですが、このカーンは無色4マナのため、現状ではもっともプレイしやすく、アドバンテージを稼いでくれます。
ただし、トークン生成能力はシナジーがないためほとんど使い道がなく、+能力もデッキ全体のカードパワーが比較的低い(1:1交換以上をとられてしまうことが多い)ため、デッキを掘り進めるくらいにしかならないこともあります。そのため、現在では格闘能力がマナクリーチャーやシステムクリーチャーに有効かつ、トークン生成能力もある情け知らずのガラクを試行中です(稲妻一発で落ちてしまうのがネックですが…)。理想はスリヴァー版の4マナギデオンのようなカードなのですが…(あるわけもなく)、引き続きこの枠は検討中です。
(5)バーン対策
集団的蛮行 2(~3)
対バーンはこちらの速度が追い付かず、かつ環境にも一定数の使用者が見込まれることから専用の枠をとっており、基本的に増呪2回のフルモードで使用することがほとんどです。できれば追加の吸管スリヴァーもサイドに採用したい所ですが、なかなかサイド枠に余裕がありません。
蛮行は対バーン以外でも対カウンターカンパニー、エルフなどにも使え、マッチアップによっては追加の手札破壊としても機能します。
以上がおおまかなサイドボードの解説です。
なお冒頭でお伝えした通り、次回で簡単にいくつかのマッチアップの in&out とゲームの進行方針をまとめて、一連の解説を終わりにしたいと思います。
あまりここでは触れられなかった対5C人間の方針などもそちらでは書きたいと思っています。
なお、当初は解説のみで終わらせる予定でしたが、せっかくなので第6回までとして、いくつかのマッチアップの in&out とゲーム進行の方針まで書こうと思います(時間はかかるかもしれませんが…笑)。
さて、スリヴァー・デッキのサイドボードはおおまかに二つの流れがあり、一つ目はスリヴァーを中心とする構成、二つ目はスリヴァーをある程度の枚数に絞って、シナジーはないけれど有効な対策カードを採用する構成に大別されます。
それぞれに一長一短があり、前者は他のスリヴァーとのシナジーを維持しているためクロックが落ちにくいものの、サイドボードの効果としては限定的、後者は効果が強力な反面、シナジーに乏しく(スリヴァーが複数体並ぶことを前提とした構築では)クロックが細くなりがち、という特徴があります。
私は後者の構成をとっており、サイドボードの機能としては、(プレイのしやすさなどは前提としつつも)刺されば1枚でも勝てる尖ったものを優先すべきだと考えています。ただ同時に、サイドボードを作る際にはそうした1枚で勝てるカードを中心としつつも、他のデッキへ転用できるカードも採用して補助する形としています。
こうした考えは、サイドボードの枚数に対してアーキタイプの数が多いモダン特有の条件下で、非常に重用だと感じています。なお、モダンのデッキが全体的に高速化する傾向もこのあたりに原因があります(=速度で上回れば〈採用枚数が限られた〉数枚の妨害はさほど問題にならない)。
効果的なサイドボードを作るには、まずは環境を渉猟してもっとも効果的と考えられるカードを探し出すことが必要ですし、このデッキにはこれ、あのデッキにはこれ…と考えるのではなく、ある程度環境のデッキを類型化し、このタイプのデッキにはこれ、といった考え方が必要になってきます。
その他、モダンは主要なアーキタイプ以外のデッキも多いため、状況にあわせて柔軟に考えられる構成や訓練も必要ですね(それでも、サイドが30枚くらい欲しくなる時がありますが…笑)。
それでは具体的に第1回の画像にあげたサイドボードを機能毎に解説していきます。
ただし、前述のようにモダンのサイドボードは15枚ではとても足らず、絶えず細部が変わっています。現段階(2018年9月)では、ブリッジヴァイン・青白コントロール・5C人間などの支配率が高いため、それぞれ、虚空の力戦の増量、思考囲いの数の調整や使用可能な専用サイドの選定(沸騰、ガドック・ティーグ、情け知らずのガラクなど…)、倦怠の宝珠の採用などの変更をおこなっています。また、M19の加入に際して、タイタンシフトに対して効果の薄かった大爆発の魔導士を高山の月に差し替えるなどの変更もおこないました。そのため必ずしも第1回の画像の通りとはならないことをご了承ください。
(1)墓地対策
虚空の力線 2(〜3)
大祖始の遺産 1
墓地対策は3~4枚をメタゲームを見て調整しています。虚空の力線の採用・枚数については疑問に思われることもあるでしょう。
まず力線を優先している理由は、単純に他の墓地対策では間に合わないケースが増えてしまったことがあげられます。
例えばグリクシスシャドウの先手・思考掃きからの2ターン目タシグルや、ドレッジの1ターン目傲慢な新生児からの発掘、ホロウワンの1ターン目虚ろな者からの炎跡のフェニックス&恐血鬼、ブリッジヴァインの1ターン目復讐蔦…など枚挙にいとまがありません。同時に青赤ストームやグリセルシュート、マルドゥパイロマンサーなどへもある程度対策になるのも大きいです。
次に枚数ですが、これは完全にサイドボードの枚数との関係です。もちろん初手にないことも往々としてありますが、それでも力線は出れば大きく有利にゲームを進められ、他の墓地対策に比べてリターンが大きいため優先して採用しています。というかそもそも、現在のモダンでは初手にない墓地対策はそれほど強くない…と割りきって使っています。ここの枚数は上記のデッキがどれくらいいるかの予想によって変動することになります。
一方、大祖始の遺産は虚空の力線とは若干用途が異なり、ジャンド(タルモゴイフ・漁る軟泥・渋面の溶岩使いなど)や青系コントロール(瞬唱の魔道士・アズカンタの探索など)対策として使うことも想定して、散らせて採用しています。対ジャンドや青系コントロールでは力線がハンドアドバンテージを失いやすくそもそもサイドインできないのに対して、遺産はドローにも変えることができて無駄牌になりにくいのが利点です。
なお、墓地対策のパターンは環境にともなって変化しており、少し前は以下の形で使い分けをしていました。
大祖始の遺産 1
虚無の呪文爆弾 1
外科的摘出 1
遺産は前述のように無駄牌になりにくい墓地対策として。他方、遺産は墓地に特化したデッキ相手だと後手で間に合わないこともあったので、呪文爆弾を(1ドローを放棄すれば)後手でも間に合う墓地対策として採用していました。また外科的摘出はグリセルシュートやアイアンワークスなど特定1種のカードを取り除くと動きが遅くなるデッキや、瞬唱を使う青系コントロール用としての役割でした。効果は限定的ですが対ドレッジ戦などでも最初の発掘カードや燃焼を追放するためにサイドインしていましたね。
(2)土地系コンボ対策
大爆発の魔道士 2(or 1枚を高山の月に差し替え)
減衰球 1
この枠は主にトロン系(緑単・青)やアミュレットタイタンなどへの対策用です。大爆発の魔道士は対コントロール、減衰球は青赤ストームやアイアンワークスへの対策としても転用できます。
ただ、以前のコントロール型のスケープシフトに対しては大爆発2枚でも対抗できましたが、タイタンシフトの登場以降、適切かつ有効なサイドを確定できていません。
大爆発1枚を血染めの太陽に差し替えたこともありましたが、トロンへの対策が薄くなることがネックで結局不採用となりました。現在はトロン・タイタンシフト双方に干渉することのできる高山の月の採用を試行中です(置物のため直接破壊するより信頼度は下がりますが…)。
(3)アーティファクト・エンチャント対策
調和スリヴァー 2
戦争の報い、禍汰奇 1
調和スリヴァーは、すべてのスリヴァーに「戦場に出たとき、アーティファクト1つかエンチャント1つを対象とし、それを破壊する」能力を共有します。
スリヴァー・デッキにとっては最上とも言えるサイドカードで、このカードのおかけで、親和(鱗親和含む)・呪禁オーラ・テゼレットコントロールなどに対して優位にゲームを進められます。
特に対親和は、サイドプランのギラプールの霊気格子にも対応でき、さらにスリヴァーの巣があれば無色のスリヴァー・トークンに能力を共有して、刻まれた勇者といったプロテクション持ちも破壊できるようになります。
その他、対トロン(忘却石など)・対青系コントロール(アズカンタの探索・拘留の宝球など)などのマッチアップでもサイドインすることができます。
ただし、この能力は再利用の賢者などと違って強制のため、場合によっては自分のものを破壊する可能性もあることに注意しましょう。また、相手の場にダークスティールの城塞などがある場合は、それを対象にとることで前述の事態を回避することができます。
一方、禍汰奇は完全に親和専用のサイドボードになります。前述の調和が3マナのため、後手で遅れないように1枚を補助用に採用しています。1度でも誘発させることができれば盤面・テンポともに大きなリターンを得られますが、相手の感電波を意識する必要やマナベースの問題もあるなど、リスクがないわけではありません。最近は鱗親和の増加など親和のバリエーションも増えつつあるので、採用する優先度は相対的に低くなっています。
(4)コントロール対策
思考囲い 2
魔術遠眼鏡 1
ウルザの後継、カーン 1(or 情け知らずのガラク 1)
思考囲いは対コントロールだけではく、対コンボや対トロン、霊気の薬瓶をサイドアウトする対ミッドレンジでのマッチアップ(ジャンド・アブザン・マルパイ…)など広範囲にサイドインできます。ただし、土地からのダメージと合わせるとダメージレース的に厳しい場合があるので、マッチアップによっては先手のみでサイドインする場合もあります。
魔術遠眼鏡は元々真髄の針だった枠で、対PWが主な役割です。以前にトリコナヒリが流行した時の名残ですが、現在も神ジェイスやテフェリー、ウギンなど対処できない=負けのPWが存在することから、枠を継続しています。
その他、献身のドルイドや渋面の溶岩使い、電結の荒廃者、鋼の監視者などのシステムクリーチャー、また仕組まれた爆薬、忘却石、ミシュラランドといったカードにも広く干渉できるため、専用サイド+αの形でサイドインが可能です。
真髄の針との優劣については、針が後手の時にも対トロンの探検の地図に干渉できたり、コストによるテンポ面で優れている面もありますが、指定を外してしまった場合のリスクを加味すると、ゲームプランを立てやすい眼鏡の方が優れている、という結論になりました。
その他、この枠としてはファイレクシアの破棄者も候補にあがります。こちらはクリーチャーのため信頼度は下がりますが、針・眼鏡と違って(土地は指定できないけれど)マナ能力も封じることができたり、薬瓶や集合した中隊との相性も良好です。とくにマナ能力も封じれる点は、クラーク族の鉄工所やカウンターカンパニーのマナクリーチャーなどへも干渉でき、サイドボードの幅が広がると思われます。
ウルザの後継、カーンは、サイド後にコントロール側がカウンターを減らす or 払拭に差し替える、あるいは全体除去を増やすことを見越して採用しています。
マナベースの関係上、スリヴァー・デッキではダブルシンボル以上のPWの採用は難しかったのですが、このカーンは無色4マナのため、現状ではもっともプレイしやすく、アドバンテージを稼いでくれます。
ただし、トークン生成能力はシナジーがないためほとんど使い道がなく、+能力もデッキ全体のカードパワーが比較的低い(1:1交換以上をとられてしまうことが多い)ため、デッキを掘り進めるくらいにしかならないこともあります。そのため、現在では格闘能力がマナクリーチャーやシステムクリーチャーに有効かつ、トークン生成能力もある情け知らずのガラクを試行中です(稲妻一発で落ちてしまうのがネックですが…)。理想はスリヴァー版の4マナギデオンのようなカードなのですが…(あるわけもなく)、引き続きこの枠は検討中です。
(5)バーン対策
集団的蛮行 2(~3)
対バーンはこちらの速度が追い付かず、かつ環境にも一定数の使用者が見込まれることから専用の枠をとっており、基本的に増呪2回のフルモードで使用することがほとんどです。できれば追加の吸管スリヴァーもサイドに採用したい所ですが、なかなかサイド枠に余裕がありません。
蛮行は対バーン以外でも対カウンターカンパニー、エルフなどにも使え、マッチアップによっては追加の手札破壊としても機能します。
以上がおおまかなサイドボードの解説です。
なお冒頭でお伝えした通り、次回で簡単にいくつかのマッチアップの in&out とゲームの進行方針をまとめて、一連の解説を終わりにしたいと思います。
あまりここでは触れられなかった対5C人間の方針などもそちらでは書きたいと思っています。
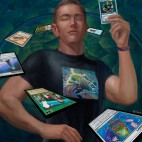
コメント